富山県南砺市福光とは?
富山県南砺市に位置する福光(ふくみつ)。
南砺市が平成の市町村合併以来、南砺市の中心として、市役所が置かれている場所であり、旧福光町です。ここは市町村合併時唯一の西礪波郡に属していた旧町です。

この町の名を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「版画の巨匠、棟方志功(むなかた しこう)が疎開し、創作活動を行った町」という事実でしょう。観光案内やガイドブックには、彼が暮らした「愛染苑(あいぜんえん)」や、作品を収蔵する「福光美術館」が必ず登場し、福光の顔として「芸術の町」が強調されます。
もちろん、それらは福光の重要な魅力の一部であり、芸術に触れる旅の大きな喜びを与えてくれます。しかし、福光の本当の姿は、その華やかな表舞台の裏に、静かに息づく別の顔を持っています。
本記事では、観光客が足を踏み入れない路地裏や、観光パンフレットには載らない郷土史の奥深さに光を当て、一歩踏み込んで町を歩くことで見えてくる、より本質的な「福光らしさ」を探っていきます。
そこには、芸術家たちにインスピレションを与え、今もなお人々の生活に根付く文化や歴史が詰まっています。
芸術の町、福光──観光記事に登場する顔
福光をインタネットで検索すると、まず出てくるのは、やはり版画の巨匠・棟方志功ゆかりのスポットです。
太平洋戦争中、戦火を逃れてこの地へ疎開してきた志功は、約6年8ヶ月もの間、福光で過ごしました。彼が創作活動を行った場所は、後の「愛染苑(あいぜんえん)」として、訪れる人々に当時の暮らしぶりを伝えています。


茅葺き屋根の古民家と、彼が日々の創作に没頭したという庭の佇まいは、静謐な空気をまとっており、志功がこの地で得たインスピレションの源泉を感じさせます。
そして、彼の作品を系統的に収集・展示しているのが、「福光美術館」です。ここでは、志功の代名詞とも言える力強い板画(はんが)だけでなく、書や陶芸作品も鑑賞でき、地域に深く根ざした彼の芸術の変遷をたどることができます。
彼の代表作である「御二菩薩釈迦御譜板画(おにぼさつしゃかおんふはんが)」をはじめ、福光の自然や人々をモチフにした作品群は、この町が彼に与えた影響の大きさを物語っています。
さらに、福光は志功だけでなく、もう一人の「美の巨人」と称される地元出身の日本画家、石崎光瑤(いしざき こうよう)を輩出しています。
彼が1940年に出品した代表作「隆冬(りゅうとう)」は、地元の福光美術館に収蔵されています。この作品は、雪が舞う冬の情景を、写実的でありながらも独自の幻想的な感性で描き出しており、雪のちらつき、曇り空、渡り鳥の群れから浮遊感を感じさせることで知られています。
福光美術館は、この郷土に縁の深い二人の巨匠の作品を展示しており、一度足を運ぶ価値のある場所です。
これらの美術館や、民芸館、そして季節ごとに開催されるアトイベントも、“芸術の町”としてのイメジを形づくっています。訪ね来る多くの人に知的な刺激と癒しを与え、福光が芸術を核とした町おこしを進めていることを示しています。
郷土史の奥深さ──観光パンフレットには載らない福光
観光地としての顔とは別に、福光にはあまり知られていない歴史や風景が点在します。
福光は、庄川と小矢部川という二つの大きな川に挟まれた盆地にあり、古くから交通の要所として栄えました。


江戸時代には、加賀藩の南の玄関口として発展し、飛騨や金沢へ通じる街道の要衝であったため、街道沿いには旅籠(はたご)や茶屋が軒を連ね、賑わいを見せていました。
当時、飛騨からは木材や炭、金沢からは米や特産品がこの地を行き交い、定期市が開かれることで、人とモノの交流が盛んに行われていました。
今も、かつての賑わいを想像させる町家造りの家並みや、ひっそりとした路地に残る石仏が、その名残を伝えています。
特に、古い「宿場町だった頃の地割」を感じさせる通りは、碁盤の目のような区画や、道幅が当時のまま残っており、往時の活気と人々の営みを静かに物語っています。
さらに時代を遡ると、戦国時代には、福光は前田氏の支配を受けながらも、隣接する飛騨との交流が盛んで、国境の町として戦略的な役割を担っていました。
その後、江戸、明治を経て、昭和には「棟方志功の疎開」という文化史的な出来事が起こります。
こうした重層的な歴史を持つ福光は、単なる宿場町や芸術の町に留まらず、「歴史・芸術・農村文化が交差した町」という独自のアイデンティティを育んできたのです。この重層的な歴史こそが、福光のもう一つの顔、町の顔と言えるでしょう。

福光らしさの核心──「人々の生活に根ざした文化」
福光の真髄は、「観光客が訪れる場所」ではなく、「生活の背景に残る文化」にあります。例えば、町のいたる所にひっそりと佇む小さな石仏は、観光のために整備されたわけではなく、人々の暮らしの一部として、今もなお大切に守られています。通りすがりの地元の人々が、花を供え、手を合わせる姿は、信仰と生活が一体となったこの町の文化を静かに物語っています。
また、豪雪地帯ならではの食文化も、福光のもう一つの顔です。福光やその周辺地域(城端、平、上平、利賀)は「特別豪雪地帯」に指定されており、冬には最大で3メトルを超える積雪が見られることもあります。
そのため、豪雪地帯ならではの保存食文化が育まれ、味噌仕込みや漬物は家庭ごとに伝統が受け継がれています。大根の麹漬けや、冬の味覚として知られるかぶら寿司は、冬の食卓に欠かせない必需品であり、観光土産にはならなくても福光や南砺市の食卓を支える大切な味です。
ニッチな魅力──一歩踏み込んだ旅で出会う風景
路地裏の町家と石仏
表通りから一本裏に入ると、福光の真の姿が顔をのぞかせます。
そこには、格子窓や虫籠窓(むしこまど)を備えた情緒豊かな町家や、堂々とした土蔵造りの建物が軒を連ね、まるでタイムスリップしたかのような感覚に陥ります。
これらの建物は、宿場町の記憶をそのまま留めており、そのひっそりとした佇まいには、時の流れが止まったかのような静寂が漂います。
そして、町を歩いていると、ふと曲がり角や祠(ほこら)の中に、苔むした小さな石仏が安置されていることに気づきます。これらは、かつて街道を行き交う旅人や、地元の人々の道中の安全を祈願して置かれたもの。
今もなお、地域住民が花を供え、手を合わせる光景に出会えます。ここにあるのは「観光のために整えられた景観」ではなく、「暮らしそのものが文化財」という福光の価値です。
志功が愛した日常の風景と新たな芸術の息吹
志功は「農作業する農民」「祭りの太鼓」「野良道の稲穂」といった何気ない日常の光景にも強い影響を受けていました。
彼は、雪の積もった田んぼの風景や、雨に濡れた畦道にさえ、生命の力強さや美しさを見出しました。彼が歩いた小道や畦道を探して歩くのも、観光パンフレットには載らない、福光ならではの楽しみ方の一つです。


古民家リノベションが生み出す新たな交流の場
近年、福光では、歴史を刻んできた古民家や蔵をリノベションした、趣ある施設が増えています。これらの場所は、過去の建物の魅力を現代の感性で蘇らせ、訪れる人々に新しい体験を提供するとともに、地域文化を次世代へと繋ぐ役割を担っています。
TSUBAKI HOUSE
福光の駅前通りからすぐの便利な場所に、1日1組限定のプライベトな宿泊施設「TSUBAKI HOUSE」があります。
この建物は、かつて地域で親しまれた伊藤歯科の旧自宅を改築したもので、築100年を超える町家の風情を随所に残しながら、現代的な快適さを兼ね備えています。
格子窓や土間など、昔ながらの建築様式が活かされた空間で、まるで歴史の中に溶け込むような滞在を楽しめます。
恒例行事の「ねつおくり」が行われる駅前通りにも歩いてすぐいける、便利な場所です。
住所:〒9391610 富山県南砺市福光69231
電話番号:08020115003
茶舎 野うさぎ
温かみのある古民家を改装した喫茶店「茶舎 野うさぎ」は、女性や家族連れに人気がありそうです。
南砺市で採れた新鮮な野菜をふんだんに使ったメニュが自慢で、まさに地産地消を体現しています。メニュにはイノシシカレや熊の油のスプなど、この地域ならではの珍しい料理も提供されており、訪れる人々に驚きと感動を与えています。
古き良き日本の家屋の雰囲気の中で、地域の恵みを味わう贅沢なひとときを過ごせます。
住所:〒9391610 富山県南砺市福光66053
Guest house 絲(いと)
福光の歴史に深く触れたいなら、古民家をリノベションした宿泊施設「Guest house 絲(いと)」がおすすめです。ここでは、以前織られていた福光麻布を織る体験(4月〜8月限定)ができます。
福光麻布は、加賀藩前田藩の特産物であり、昭和天皇の大喪の礼に調達されるほどの献上品でしたが、織物事業の衰退には勝てず生産が終わった歴史があります。
この伝統技術を現代に伝える貴重な場所です。
住所:〒9391610 富山県南砺市福光62242
電話番号:070-4390-3638
The Guest House 美知の里
自然豊かな南砺市下野に位置する「The Guest House 美知の里」は、もともと築100年の蔵だった建物をリノベションしたユニクな宿泊施設です。
ここでは、蔵の重厚な雰囲気を活かしつつ、女将さんの手作りによるBBQ、石窯ピザ、燻製などが楽しめます。
家族や気心の知れた親友と一緒に夏休みに泊まると、手作りの温かさが感じられる空間で、特別な思い出を作ることができるでしょう。
住所:〒9391733 富山県南砺市下野285
電話番号:090-3760-8345
職人の町、福光──暮らしを支える伝統技術
福光には、和紙や箪笥(たんす)づくりといった伝統工芸の技が今もなお息づいています。これらは大量生産品ではなく、地域に根ざした手作りの品であり、地元の生活を支える実用品です。
中でも特筆すべきは、木製バットの生産です。今から約50年前に、読売ジャイアンツの王貞治選手がホムラン数の世界記録を打ち立てた時代に使われていた木製バットは、福光で生産されたものだったようです。
2012年にできた「南砺バットミュジアム」では、プロ野球界で大活躍した選手たちの貴重なバットを見ることができます。
長嶋茂雄、王貞治、金本和憲、イチロ―など、往年のスパスタが実際に使ったバットが展示されており、野球ファンには垂涎ものの展示品ばかりです。
福光には、このような卓越した技術を持つ職人たちがたくさんいるのが特徴です。
福光の“静けさ”の価値
金沢や高岡のような華やかで観光客で賑わう都市に比べると、福光は控えめで、どこか静けさをまとった町です。しかし、その静けさこそが、福光の最大の魅力であり、価値と言えるでしょう。
それは、観光客のために演出された人工的な賑わいではなく、「人々の生活そのもの」から生まれる、本物の静けさです。田んぼで農作業に励む人の姿、雪に包まれた冬の町並み、路地裏にひっそりと佇む石仏……。
ここにあるのは、ありのままの暮らしの風景です。
福光の最大の魅力は「人」にあります。木工や和紙職人、農家、そして芸術家。彼らの日常は観光用に演出されたものではなく、普段の暮らしそのものです。
旅人が工房や農家を訪ね、直接会話を交わすことで、町の奥行きを実感できます。
福光を深く知るためのモデルコ-ス(ニッチ版)
せっかく福光を訪れるなら、観光パンフレットには載っていない、一歩踏み込んだ旅を体験してみませんか。
一つモデルコースを挙げてみましょう。
午前:旧宿場町の路地散策(町家・石仏めぐり)
昼:地元食堂で郷土料理のランチ
午後:古民家ギャラリや工房を訪問
夕方:古民家カフェで一息
このモデルコスは、観光名所を駆け足で巡るのではなく、ゆっくりと「暮らしに溶け込む旅」を提案するものです。
写真撮影ガイド
路地裏の格子窓や石仏: 午前の柔らかな光で撮影すると、陰影が美しく際立ちます。
農作業風景: 秋の収穫期がおすすめです。黄金色の稲穂と働く人々の姿は、福光の豊かな風土を象徴します。
里芋料理や地元食堂の一皿: 湯気を含めて撮影すると、温かさが伝わります。
古民家カフェ: 木の温もりを強調すると、空間の居心地の良さを表現できます。
まとめ
福光は「棟方志功と芸術の町」という一つの顔だけでは語り尽くせない、奥深い魅力を持った町です。宿場町としての歴史、路地裏に残る文化、農と工芸が結びついた暮らし——その一つひとつが福光の本当の姿です。
観光客が少ないからこそ、静かに歩き、人と触れ合い、文化の厚みを感じられます。それが福光を旅する最大の魅力であり、本当の「豊かさ」を見つける旅になるでしょう。


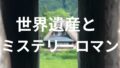
コメント