南砺市城端とは
城端は「越中の小京都」とも呼ばれます。この呼称は、城端の町が持つ 宗教・芸術・町衆文化の融合 に由来しています。善徳寺を中心に町が形成され、門前町文化が花開いた点は、京都・東本願寺の町割りとよく似ています。
また、曳山祭に見られる雅な意匠、町家が並ぶ格子戸の美しさ、職人の手仕事と芸能が共存する気風がいずれも京都の伝統文化に通じる「美意識と精神性」を宿しているのです。今回は9月の秋空の午後に城端をふらっと訪ねてみました。
城端の文化 善徳寺としげ絹

街を歩いて分かるのは、中心がこの善徳寺だということです。JR城端駅からこの善徳寺までおよそ650mの距離にこの善徳寺があります。
城端の歩みを語るなら、まず善徳寺の移転・成立が転機でした。善徳寺は室町時代に建立され、加賀藩から保護を受け、越中地方における浄土真宗の触頭(ふれがしら)寺院として、地域の宗教的・社会的な要地となりました。善徳寺と城端の町衆は、ただ信仰を支えるだけでなく、相互に育み合う関係でした。寺を訪れる参詣者を受け入れる宿屋・商家が自然に集まり、門前町が形成され、町家と織物産業が密接に結びついて町の構造ができあがったのです。



同時に城端には、養蚕・絹織物という産業的軸も存在しました。城端で始まった絹織物の伝承は、戦国後期(約430〜440年前)に畑氏による始まりの伝承を持つとされ、城端絹は天正時代以降、加賀藩によって庇護されて「加賀絹」としても知られるようになりました。



特筆すべきは、「しけ絹(しけぎぬ)」という城端ならではの絹織物の存在です。通常、蚕は一頭で一つの繭を作りますが、ごく稀に二頭の蚕が協働して一つの繭を紡ぐ「玉繭(ぎょくまゆ)」という現象があります。この玉繭から紡いだ糸は節が多く不均一な太さとなり、その独特の風合いが織物に現れます。これを活かして織り上げられた織物がしけ絹です。
現在、城端では松井機業のみらしく、しけ絹を扱う事業者は国内で2社しかないとされています。[1]松井機業は明治10年(1877年)創業。長年に渡って絹織物を継承してきた工房であり、今も城端絹・しけ絹を中心に織物を作り続けています。機屋の音が町じゅうに響いていた時代、城端ではかつて、戸数689軒中375軒が織物に関わっていたという史料も残っています。
このシゲ絹に関してはじょうはな絹館がこの格子戸家屋の並びに建っていて、中ではしげ絹の歴史を学んだり、実演を見学できたりするらしいですが、今回は外見だけ見ておきました。館内のショップでは、しけ絹を使った小物やストール、アクセサリーなどが販売されています。お土産としても人気が高く、「伝統を持ち帰る旅」を楽しめるらしいです。
これらの文化・産業的背景が、城端の町並みに深く刻まれています。たとえば、町家の屋根裏(アマ:屋根裏部屋)は、採光・通風・温度管理を兼ねて、養蚕作業に適する構造を持つように造られたという記録もあり、養蚕が住居構造にも影響を与えていたことがうかがえます。
越中の小京都 城端 格子戸家屋の町並み
そして、この町割りは今も江戸時代の姿を色濃く残しています。特に城端別院善徳寺から門前町通りを経て町並み保存地区に至る通路は、黒光りする格子戸家屋が続く景観が続きます。木格子の隙間から漏れる暮らしの灯り。土蔵造りの白壁と黒漆喰壁が交錯し、道端には暮らしの痕跡として植木鉢、竹箒、干し物などが無造作に置かれています。細い石畳の小路へ入れば、雨に濡れた石が青く光り、古い看板が軒の庇から風に揺れ、静かな時間を刻んでいるようです。


観光用に整備された町並みエリアとは異なり、城端ではこの通り沿いに今も日常生活が溶け込んでいます。洗濯物が格子戸に寄りかかるように干され、夕餉の匂いが風に混ざり、格子の奥で猫がひとときの昼寝をしています。この町並みは、歴史が眠る舞台ではなく、今を生きる生活の表情なのです。そして町並みと自然は密接に共存しています。山並みがすぐ背後に迫り、夕暮れには山影が町をじっと包み込む。風が吹けば木々の葉が揺れ、そのざわめきが町家の屋根を伝わり、時折木戸の隙間に入り込んできます。人と自然が呼応し合う風景。それが城端の町並みの空気です。
実際歩いてみると分かりますが、あまり人が歩いていないのでゆったりブラブラできます。善徳寺前の道は風情があって郷愁感も感じる場所でした。メイン道路の304号線を一つ外れた街の小道に入っても、格子戸になっているので雰囲気があります。
ユネスコ無形文化遺産・城端曳山祭

城端を代表する文化といえば「曳山祭(ひきやままつり)」です。毎年5月4日・5日に行われるこの祭りは、江戸時代中期から続く長い歴史を持ち、2016年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。[2]
全国各地に曳山祭は存在しますが、城端の祭りは「曳山」と「庵屋台(いおりやたい)」の両方が登場する、極めて珍しい形式を持っています。
華やかさと職人技を競う「曳山」
曳山は、高さ6メトル近い車輪付きの山車に、金箔や漆、精緻な彫刻をあしらった豪華絢爛なものです。その姿は「動く美術館」とも形容され、町ごとに趣向を凝らした装飾が施されています。龍や鳳凰など縁起物を題材とした彫刻、金糸を織り込んだ幕、天井画などが見どころで、職人たちの粋と技術が結集しています。
曳山の巡行は、単なる見世物ではなく「町衆の誇り」を象徴しています。各町内に保存会があり、祭りの維持や修復を担っているのも町人たち。代々受け継がれる意匠とその誇りが、曳山の豪華さを支えているのです。
幽玄さをたたえる「庵屋台」
一方で、曳山と対照的な存在が「庵屋台」です。藁葺き屋根や障子戸を備えた小さな屋台で、中では三味線や謡、胡弓といった芸能が演じられます。扉が閉じられると、観客は外からわずかな音や灯りを感じ取るだけ。派手さとは正反対の、静寂と幽玄の世界が広がります。
夜になると庵屋台は提灯の灯りに浮かび上がり、通り全体が幻想的な舞台に変わります。三味線の音色や唄声が町並みに溶け込み、観る者は「非日常の静けさ」に包まれます。この「動と静」「華やかさと幽玄」の対比こそが、城端曳山祭の最大の魅力です。
町衆文化と世代継承
城端曳山祭の特徴は、観光化されすぎていない点にもあります。もちろん観光客は訪れますが、主役はあくまで地元の町衆。曳山を曳くのも庵屋台を支えるのも、城端の人々です。近年では若者の参加も増え、地域全体で祭りを未来に引き継ごうという空気があります。
町衆にとって曳山祭は「外に見せるため」ではなく、「自分たちの誇り」を再確認する場なのです。その意味で、この祭りは観光資源である前に、地域文化の心臓部といえるでしょう。
町全体で体感する曳山祭
曳山の豪華さと庵屋台の静謐さ。城端曳山祭は、その二つが交差することで、町全体を劇場のように変えてしまいます。日常の町並みが、この二日間だけは非日常の舞台に生まれ変わる。そこに、城端という町の文化的な奥深さが凝縮されています。
この祭りは「見る」ものではなく、「町そのものを体感する」文化体験なのです。
城端 曳山祭の開催日と城端曳山会館
■ 曳山祭の開催日
城端を代表する「城端曳山祭(じょうはなひきやままつり)」は、
毎年5月4日・5日 の2日間に開催されます。
-
開催地:富山県南砺市城端地区(城端別院善徳寺周辺)
-
主催:城端曳山祭保存会
-
起源:江戸時代中期(約300年前)
-
登録:2016年 ユネスコ無形文化遺産
初日の夜(5月4日)は庵屋台の曳き出しが行われ、夜の提灯の灯りに照らされた屋台が通りを進む様子は「幻想的な舞台」として人気です。翌5日には、曳山7基が町を巡行し、三味線や謡が響くなか、町全体が祭り一色に染まります。
見どころポイント
-
善徳寺前の巡行(昼)
-
南砺市城端庵屋台通りの提灯行列(夜)
-
曳山会館前のすれ違い場面(写真スポット)
■ 曳山祭を見られない時期のおすすめ体験
「5月に行けない」「祭り当日は混雑が苦手」という方でも、城端の文化をしっかり体感できるスポットがあります。
🏛 城端曳山会館(じょうはなひきやまかいかん)


祭りを年間通して体験できる施設。本物の曳山が常設展示されており、内部に入って彫刻や装飾を間近で見ることができます。
-
庵屋台の再現展示:内部に入り、三味線や謡の再現映像を体感可能。
-
祭り映像コーナー:夜の庵屋台巡行を大型スクリーンで再現。
-
職人技の紹介:曳山彫刻・漆塗り・金具細工などの解説展示あり。
🕒 開館時間:9:00~17:00(年中無休)
🎫 入館料:大人520円、高校生以下無料(南砺市民割引あり)
→ 5月以外でも“いつでも曳山祭を体験できる場所”として、観光客から高い評価を得ています。
☕ 町歩き+文化体験ルート
曳山祭がない時期でも、町全体が「祭りの残り香」を感じさせてくれます。
-
善徳寺から町並み保存地区を歩くと、曳山の彫刻モチーフと似た意匠を町家に見つけられる。
-
曳山会館周辺のカフェや和菓子店では、曳山を模したお菓子やグッズも販売。
-
秋(9月)には「麦屋まつり」が開かれ、民謡「麦屋節」が響く夜もおすすめ。
📅 おすすめ時期
-
春(4月中旬〜5月上旬):桜ヶ池の桜と合わせて訪問
-
秋(9月下旬〜10月):麦屋まつり・紅葉シーズン
アニメ「true tears」とドラマ「最愛」の町
城端の魅力は、伝統文化だけにとどまりません。実はこの町は、現代の映像文化においても注目を集めています。アニメやドラマの舞台に選ばれることが多く、全国からファンが訪れる“聖地”となっているのです。
アニメ「true tears」の巡礼地
2008年に放送されたアニメ『true tears』は、恋と青春をテマにした作品ですが、その舞台モデルの一つが城端でした。善徳寺の参道や町並み、城端駅周辺などが劇中に登場し、放送終了から十数年経った今でも、全国からファンが“聖地巡礼”に訪れていると聞きます。
この作品を手がけたのは、富山県南砺市に本社を構えるアニメ制作会社 P.A.WORKS(ピ―エ―ワ―クス)。創業者の堀川憲司氏は「地方からでも良質なアニメを発信できる」という信念を持ち、あえて地元・城端に拠点を置きました。その思いは作品にも反映され、『true tears』の背景美術には、善徳寺や城端の古い町並みが精緻に描かれています。
この作品はP.A.WORKSが初めて「元請け制作」を担当した記念すべき作品でもあり、会社と城端の両方にとって出発点となりました。放送後には、城端でファンイベントや記念企画が相次いで開催され、全国から訪れたアニメファンと地元の人々が交流する光景が生まれました。曳山会館や商店街にはパネル展示やコラボ企画が行われ、アニメ文化が町おこしの一助となりました。

アニメファンが町を歩く姿は、地元の人々にとっても日常の風景になりつつあります。町家の格子越しにキャラクタのイラストが飾られたり、カフェでコラボメニュが提供されたりと、伝統的な町並みとアニメカルチャが自然に共存しているのが城端の面白さです。ファンイベントをきっかけに地域活性化へとつながった点では、単なる聖地巡礼を超えて、現代文化と町衆文化の新しい関係性を築いた例といえるでしょう。



城端が TBSドラマ『最愛』ロケ地に選ばれた理由と魅力

さらに2021年には、TBSドラマ『最愛』の主要ロケ地として城端が全国の注目を浴びました。善徳寺の参道、古い町並み、そして城端駅などが撮影に使われ、視聴者に「美しい町並み」として強い印象を与えました。ドラマ放送後は「ここがあのシ―ンの場所だ」と訪れる人も増え、城端は再び“映像で見た町を訪れる旅”の目的地になっていたといいます。
ドラマ『最愛』が城端をロケ地に選んだ理由を考えると、単なる “美しい町並み” というだけでは語れない、城端ならではの映像的魅力と文化の重層性が浮かび上がります。
たとえば、梨央の通学シ―ンに使われた城端駅。木造駅舎、ホムに佇む列車、静かな終着駅の佇まいは、ノスタルジと時間を含む空気感を映像に宿します。

また、城端醤油株式会社前でのシ―ンも記録されており、弟・優と友人との喧嘩が起こる場面として使われました。建物は縦格子、瓦屋根、趣ある看板を備えており、物語世界への没入感を強める背景として有効だったはずです。
さらに坡場の坂と呼ばれる通りも、通学路や柵を乗り越える場面に登場。細い坂道・町家建築・路地感覚のある背景は、物語の緊張や感情を写しとる画を可能にしました。
これらの場所の選定から見えてくるのは、城端が「単なる古い町」ではなく、映像表現に耐える重層的な町並みを持つ町であるということです。城端は物語を映すキャンバスとして機能し、視聴者を物語世界へ引き込む空気を持っているようです。

未来への挑戦──癒しロボ「パロ」と地域活性化
城端は、善徳寺や曳山祭といった歴史文化だけの町ではありません。近年は少子高齢化や人口減少といった課題に直面しつつも、未来を見据えた挑戦を続けています。その象徴が、アザラシ型セラピロボット「パロ(Paro)」です。
パロは人工知能を備えた癒しロボットで、人の声や触れ方に反応して鳴いたり身じろぎしたりします。世界50カ国以上で導入され、認知症ケアやストレス緩和、災害被災者や避難民の心の支援に使われるなど、国際的にも高く評価されています。テレビ番組や新聞でもたびたび取り上げられ、海外の子どもたちや高齢者の笑顔を引き出す存在として注目されてきました。
万博に登場する城端発のロボット
2025年の大阪・関西万博でも、パロは5月4日から10日の「赤十字ウィ-ク」に展示されました。国際的な舞台で、南砺市・城端から生まれたロボットが紹介されるのは、町の未来を象徴する大きな出来事です。観光や伝統文化の発信に加え、「福祉とテクノロジの発信拠点」としての新しい城端像を世界に示す機会となっています。
城端へのアクセスルートとおすすめ旅プラン
■ 鉄道で訪れる場合(公共交通)
城端は、富山県南砺市の南部に位置し、JR城端線の終着駅「城端駅」が玄関口です。
-
富山駅 →(あいの風とやま鉄道 約25分)→ 高岡駅
-
高岡駅 →(JR城端線 約1時間10分)→ 城端駅
のルートが一般的です。
途中、田園風景や山並みが車窓に広がり、のどかな「ローカル線の旅」を楽しむことができます。
終着駅の城端駅は木造駅舎で、アニメ「true tears」とドラマ「最愛」のロケ地としても知られています。
●ポイント
-
高岡駅発の列車は1時間に1本程度。時間に余裕をもって計画を立てましょう。
-
城端駅から善徳寺や曳山会館までは徒歩10〜15分ほど。町歩きにぴったりの距離です。
-
城端線には観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール(愛称:べるもんた)」が走る日もあり、車窓からの景観と地元グルメが楽しめます。
■ 車で訪れる場合(ドライブ観光)
自動車でのアクセスも非常に便利です。
-
北陸自動車道「福光IC」から約10分
-
東海北陸自動車道「五箇山IC」から約20分
-
金沢市内から約1時間30分、富山市内から約1時間
高速道路の出口から主要観光地までは国道304号線(別院通り)を経由してアクセスできます。
駐車は「城端曳山会館」前の観光駐車場や「城端駅前駐車場」を利用するのが便利でしょう。
●ポイント
-
曳山祭の開催日(5月4〜5日)は交通規制が入るため、公共交通を推奨。
-
冬季は積雪があるため、スタッドレスタイヤまたは公共交通利用をおすすめします。
■ 高速バス・レンタカーで訪れる場合
-
高速バス:東京・名古屋・大阪方面からは「城端サービスエリア」に停車する便があります。
SAからはタクシーまたは南砺市コミュニティバスで城端中心部へ(約10分)。 -
レンタカー:富山駅・金沢駅からのレンタカー利用なら、
途中で「井波」や「五箇山」などを巡る周遊ルートが人気です。
■ 周遊ルートのおすすめ
旅をより充実させるなら、「南砺市カルチャールート」として以下の順番がおすすめです。
-
井波(木彫刻と瑞泉寺)
-
福光(棟方志功記念館)
-
城端(善徳寺と曳山祭、町並み散策)
-
五箇山(合掌造り集落 世界遺産)
いずれも車で20〜30分圏内にあり、1日で“南砺の文化地層”を巡る旅が可能です。
特に「井波→城端→五箇山」は、木の文化・信仰文化・生活文化が三位一体で体感できるルートとして、国内外の旅行者に人気があります。
■ 旅のアドバイス
-
町並み散策は午前〜夕方の明るい時間帯がおすすめ。
-
夕暮れ時は善徳寺通りの格子戸越しに灯りがともり、「越中の小京都」と呼ばれる理由を感じられます。
-
滞在時間の目安:曳山会館・善徳寺・町並み散策・絹館を含めて約3〜4時間。
まとめ:過去と未来が交差する「城端歴史体験」
城端は、単に「古い町並みが残る観光地」ではありません。室町時代から続く善徳寺の門前町としての歴史、ユネスコ無形文化遺産・曳山祭に象徴される信仰と美意識、そしてアニメ『true tears』やドラマ『最愛』が描き出した映像文化。さらに、世界50カ国で活用される癒しロボット「パロ」を生み出す株式会社知能システムという未来志向の存在まで——。
ここには、過去・現在・未来の物語が同じ地層のように折り重なっているのです。
町を歩けば、格子戸の町家や石畳の路地の向こうに、アニメの舞台となった風景や、ドラマで見た坂道が広がっています。そしてそのすぐ近くで、世界へ向けて未来を描く技術が育っている。これほどまでに文化と時間が交錯する町は、全国を見渡してもそう多くはありません。
だからこそ城端は、観光スポットとしてだけでなく、「文化の交差点」そのものを体験できる町なのです。歴史に触れ、現代カルチャを感じ、未来への挑戦を知る。そんな三層構造の旅は、南砺市のなかでも城端ならではの特別な体験となるでしょう。
富山を訪れるときは、ぜひ城端を歩いてみてください。過去と未来が交差する町で、あなた自身の新しい発見が待っています。
参考・出典
- 松井機業「会社案内」…「国内では二軒しか作れないしけ絹」等の記述。
城端絹 | 松井機業しけ絹を利用したインテリア商品や斜子・紋紗などの表具地、和装用夏用襦袢として使われる駒絽などの 小幅織物を製造しております。しけ絹の新しい楽しみ方を提案する「JOHANAS(ヨハナス)」 - UNESCO「Yama, Hoko, Yatai, float festivals in Japan」…2016年登録の公式記載。
…01059ICH - UNESCO Intangible Cultural HeritageExplore UNESCO’s Intangible Cultural Heritage: policies, lists, best practices, and resources for its safeguarding and g...

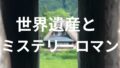

コメント